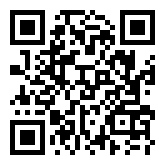不動産用語集
あ行
IHクッキングヒーター
電磁調理器(でんじちょうりき)とは、内部に配置されるコイルに流れる電流により、所定の種類の金属製の調理器具を自己発熱させる、加熱のための器具である。加熱原理は誘導加熱(英語: induction heating、IH)であり、IH調理器とも呼ばれる。ガスや火を使用せず、電力のみで動作する。一般的には、コンロ型をしている調理器具を言う。IH炊飯器などの、同じ加熱原理を用いる機器を含めることもある。
IHクッキングヒーターと言った場合は、コンロ型の調理器を限定して指す場合が多い。
アイランドキッチン
壁から離れたところに独立した作業台を設置した台所。作業台に流し台やコンロを配置することもある。
島のように見えることからアイランドキッチンと呼ばれる。
アウトフレーム工法
アウトフレーム工法とは、マンションの住戸の四隅を支える太い柱や梁を、住戸の外側に出す工法。
室内に柱や梁の出っ張りがなくなり、部屋の四隅まで有効に使えるのがメリット。アウトポールともいう。また、通常とは逆に梁の下に床スラブを配置し、柱をバルコニー側に出したものを「逆梁アウトフレーム工法」と呼ぶ。
青地
登記所に備え付けられている公図上青く塗られた部分のことで、国有地である水路や河川敷を示すものです。
本来は一般の宅地にはならないが、水路が事実上廃止されるなどして、青地を含む敷地上に住宅が建っていることもあります。
このように、敷地内に青地を含む住宅を購入する場合には、青地を国から払い下げてもらう手続きを要することがあります。
青田売り
青田売りとは、造成工事や建築工事が完了していないのに、宅地や建物の販売などをすることをいいます。未完成販売ともいいます。
赤道
公図上で地番が記載されていない土地の一つで、道路であった土地をいう。
古くから道路として利用された土地のうち、道路法の道路の敷地とされずにそのまま残った土地がこれに該当し、国有地である。公図に赤色で着色されていることから「あかみち」と呼ばれている。
アスベスト
石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。
その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が 吸入してしまうおそれがあります。以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止さ れました。
その後も、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などで使用されましたが、現在では、原則として製造等が禁止されています。
石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。
頭金
マイホームを購入するときに、用意してある自己資金のこと。
頭金が多いとローン借り入れ額を減らせるため月々の支払いや利息を抑えることができます。
RC造
鉄筋コンクリート構造(てっきんコンクリートこうぞう)とは、鉄筋コンクリートを用いた建築の構造もしくは工法。英語のReinforced-Concrete(補強されたコンクリート)の頭文字からRC構造またはRC造と略される。ジョゼフ・モニエが発明し、パリの再開発に貢献した。20世紀に世界で実用化された。日本では関東大震災の経験から広く使用されるようになった。
大別して、柱と梁で構成するラーメン構造と、壁面と床版など平面的な構造材で構成する壁式構造の二つがある。実務上は低層建物の場合、これらを組み合わせた壁式ラーメン構造である事も多い。以前は高層ビルといえば、鉄骨鉄筋コンクリート造であったが、技術の進化により高強度コンクリートを使用した、純粋な鉄筋コンクリート構造での高層ビルも多い。
一般媒介契約
一般媒介契約とは媒介契約の一種で、依頼者(売主)が複数の宅建業者に重複して依頼できる媒介契約をいいます。
依頼者は、1業者に限定することなく媒介を依頼でき、また、自ら取引相手(顧客)を探して売買や賃貸借契約を結ぶこともできます。この契約には、当初依頼した業者に対して、重複して依頼した他の業者に関して、明示する義務があるもの(明示型)と、明示する義務のないもの(非明示型)とがあります。
依頼を受けた業者にとっては、他の業者に対して独占的にその取引の媒介業務を行うことはできませんが、業者間で物件情報を共有することで、物件を探している顧客に対しては、幅広い情報の中から紹介できるというメリットがあります。
違約金
契約に定めた事項に違反(債務不履行)した者が、相手方に対して支払う金銭のことを違約金といいます。一種の制裁金(違約罰)です。
一般に、債務不履行があった場合、債権者は債務者に損害賠償を請求することができますが、債権者は損害の有無や損害額などを証明しなければならないことになっています。これは、非常に煩わしいことなので、あらかじめ損害の額を予定しておくのが便利ということで、違約金が決められるようになったのです。
なお、違約金は民法上の「損害賠償の予定」とみなされていますので、違反者が支払うのは、実際の損害とはかかわりなく、違約金のみとなります。また、売主が宅建業者で買主が個人、もしくは宅建業者が売主で個人が買主の場合、違約金は総額の2割を超えることができないようになっています。
印紙税
印紙税(いんしぜい)は、印紙税法に基づき、課税物件に該当する一定の文書(課税文書)に対して課される日本の税金。
不動産取引に関しては主に、不動産売買契約書と金銭消費貸借契約書が課税文書にあたる。
ウォークインクローゼット
ウォークインクローゼットとは、主に洋室に設けられる洋服などをしまう収納スペースのことで、内部にはハンガーをかけるハンガーパイプ
内法面積
内法面積とは『壁で囲まれた内側だけの建物の床面積』をいいます。壁や柱の厚みは含まずに、実際の住居スペースのみで計算した面積です。不動産登記法では、この内法面積で測定します。
登記簿謄本に記載されている面積は、この「内法面積」です。
エクステリア
住宅敷地まわりのエクステリアを指す場合には一般に屋外構造物の門扉、塀といった外柵、車庫などのほか、庭とそこに設置されるウッドデッキ、植栽、その他の設備なども含め敷地内の外部空間全体をさす。
エコカラット
微細な孔を持つ原料をタイル状に焼いてインテリアで使用できるようにしたものです。 この微細な1ナノメートル(1mmの百万分の1)の孔に空気中の湿気が入ったり出たりすることで、湿気を吸収したり放出したりして湿度を変化させる働きをしていると考えられています。
SRC造
SRC造とは、鉄骨鉄筋コンクリート造(Steel Reinforced Concrete)の略で、鉄筋コンクリートに鉄骨を内蔵させた建築構造のことです。
エントランス
正面玄関に面した建物の出入口をいいます。 最初に人を迎え入れる所で、建物の顔ともいえる空間です。
ALC
高温高圧で蒸気養生された軽量気泡コンクリート。一般的にはパネル状に成型され、鉄骨造の外壁・屋根・床・間仕切壁などに使用される。軽量で断熱性や耐火性などに優れている。外壁パネルはさまざまなデザインの意匠パネルが用意されている。
追い炊き
ガス風呂給湯器やガス風呂釜の機能の一つで、浴槽内の湯が冷めたときに、さし湯をせずに沸かし直すことができる機能。 風呂の追いだきと、シャワーや台所・洗面室などでの給湯を同時に利用できるタイプとそうでないタイプがある。
おとり広告
客寄せのための架空広告のこと。 最も悪質な不当表示として、広告規約で禁止されている。
実際には存在しない架空物件の広告、または存在しても広告内容と実物が異なるものなどが該当する。
オーナーチェンジ
現に居住している賃借人をそのままにして不動産物件を売買することをいいます。 賃貸借契約を継続した状態で、所有者(オーナー)だけが代わるために「オーナーチェンジ」と呼ばれるのです。
オープン外構
道路との境界線を塀や門扉で囲わないものを言います。 欧米には多いスタイルで、明るく開放的なのが魅力です。 芝生やタイル、石張りなどで敷地を示すものや、花壇や低い植え込みで境界線を示すものなど様々なバリエーションがあります。
オープンキッチン
「開けた台所」、つまりキッチンが壁で仕切られることなくダイニング、さらにはリビングともつながっているキッチンを指します。 多くの魅力を持つキッチンタイプの1つであることから、近年住まいに取り入れる方が非常に増えています。
オール電化
オール電化住宅とは、IHクッキングヒーターやエコキュートなどの機器を導入することで調理・給湯・冷暖房などに用いるエネルギーを全て電気によってまかなうシステムを備えた住宅 。
か行
開発道路
開発許可を得た開発区域内の道路のことです。
開発許可制度の適用を受けるものは、開発道路として建築基準法第42条第1項第2号の道路となります。 開発道路は所有権が市町村に移管されるケースが多く、移管後は公道扱いとなります。
解約
契約を取り消すこと。
家屋番号
家屋番号とは、不動産登記法の規定に基づき、管轄法務局が同法上の建物に付する番号をいう。いわば建物一つ一つを識別するための固有の番号である。
住居表示に関する法律の規定に基づき市町村が付する住居番号とは異なる。
火災保険
損害保険の一つで、建物や建物内に収容された物品(住宅内の家財用具、工場などの設備や商品の在庫など)の火災や風水害による損害を補填する保険である。
瑕疵担保責任
瑕疵担保責任とは売買の目的物に瑕疵(その物が取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態)があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気付かぬものである場合に、売主が買主に対して負う責任をいいます。
壁芯面積
壁芯とは、壁の中心線を結んで測った寸法のこと。 内法に比べ、壁の厚みの分だけ面積は大きくなる。 分譲マンションのパンフレットに書かれた専有面積は壁芯計算によるものが多く、実際に使用可能な面積はそれより少し狭い。 公的融資を受ける時には壁芯による面積、税金の軽減措置に必要な要件は内法による面積なので注意が必要。
仮換地
土地区画整理事業の工事中、従前の宅地の代わりに使用できるように指定された土地のことをいいます。 仮換地を使用できるのは、仮換地指定の効力が発生した時から最終的な換地処分の公告がされる時までです。 この期間は、仮換地を従前地と同様に使用収益することができます。
換地
区画整理を行い新しい土地をもらいます。この新しい土地、区画整理によって割り当てらた土地を換地と言います。
換地処分
換地計画にかかる区域の全部について、土地区画整理工事が完了した後に、従前の宅地所有者等に対して、換地(新しい土地)を割り当てることを換地処分と言います。
管理会社
管理会社とは、管理組合からマンションの管理を委託された管理の専門業者のこと。 業務内容は、住人からの管理費・修繕積立金等の回収や滞納などのチェック業務、理事会や総会の運営支援、清掃やゴミ出し、設備機器の保守点検、備品の管理、マンションの巡回、業者の立ち会いなど多岐にわたる。
管理規約
マンションなどの区分所有建築物で、マンションの管理運営について管理組合が定めるルールを「管理規約」といいます。
専有部分や共用部分の範囲、理事会や会計に関する事項などの基本部分は、区分所有法に則り、細かい項目については、個別のケースの実情に合わせて定めます。
管理組合
建物の区分所有等に関する法律に基づき区分所有建物(分譲マンションなど)を区分所有する区分所有者によって構成される団体である。
管理費
分譲マンションの敷地や建物の共用部分、共同で使用する施設や設備などの維持管理に必要な経費のこと。 例えば、エレベーターの点検、共用部分の清掃、管理員の窓口業務、共用部分の光熱費などである。
外構
外構とは、居住、生活する建物の外にある構造物全体を指す言葉である。それには門、車庫、カーポート、土間、アプローチ、塀、柵、垣根、などの構造物、それに庭木、物置なども含まれる。
合筆
合筆とは隣接する数筆の土地を一筆の土地に法的に合体することをいう。対義は分筆。
危険負担
危険負担とは後発的な理由によって、目的物に何らかの損害が生じた場合における損害の割合のこと。
売買契約後に地震や災害などによって建物に損害が生じた場合など。
既存宅地
市街化調整区域内の土地に対する制限を緩和し、その土地が「市街化調整区域とされた時点で既に宅地となっていた」などの条件を満たした場合に、建築行為許可を免除する制度である。2001年5月18日をもって廃止された。
既存不適格建築物
建築時には適法に建てられた建築物であって、その後、法令の改正や都市計画変更等によって現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことをいう。 建築基準法は原則として着工時の法律に適合することを要求しているため、着工後に法令の改正など、新たな規制ができた際に生じるものである。
融資を受ける際に不利になることが多い。
規約敷地
区分所有法により、区分所有者の規約によって区分所有建物の敷地とされた土地で、区分所有者が建物および建物が所在する土地と一体として管理または使用をするものをいう。
建物の敷地ではないが、庭園、通路、駐車場など、建物の敷地と一体的に利用される土地がこれに該当する。規約敷地は、区分所有建物の敷地(法定敷地)と同様に区分所有者の共有とされ、原則として専有部分と分離して処分することはできない。
旧法借地権
借地借家法が施行された日(1992(平成4)年8月1日)より前に成立した借地権であって、旧借地法にもとづく借地権のこと。
借地借家に関する法制度は、かつては借地法・借家法の二本立てであったが、1992(平成4)年8月1日に借地借家法が施行されたことにより、一本化された。
供託
金銭・有価証券・物品を供託所や一定の者に差し出し、保管してもらうこと。
共有持分
複数の人が一つの物を共同で所有しているとき、それぞれの人がその物について持っている所有権の割合を「共有持分」という。 例えば、相続が発生して、3人の子が1つの土地を相続したとき、遺産分割をする前の時点では、各相続人のその土地に関する共有持分は「3分の1」である。
共用部分
共用部分 とは、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがある場合において、その各部分に属さないもので、付属施設を含むものをいう。
金銭消費貸借契約
将来の弁済を約束した上で、金銭を消費するために借り入れる契約のことである。
主に住宅ローンなど。
クッションフロア
ビニール製のクッション性のあるシート状床材。 裏打ち材に不織布やビニール層があり、中間に発泡層、表面に透明ビニールなどを張り合わせたもの。
区分所有権
マンションやオフィスビルなどのように、建物の中に独立した複数の住居や店舗、事務所などがある場合、それぞれの独立した部分の所有権を区分所有権といいます。
クーリングオフ
一定の契約に限り、一定期間、説明不要で無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度である。ただし、申込者が商人または契約が開業準備行為であるものに対しては、適用されない。
建築確認
建築基準法に基づき、建築物などの建築計画が建築基準法令や建築基準関係規定に適合しているかどうかを着工前に審査する行政行為である。
建築条件付土地
所有する土地を販売するに当たり、土地購入者との間において、指定する建設業者との間に、土地に建築する建物について一定期間内に建築請負契約が成立することを条件として売買される土地の建築請負契約の相手方となる者を制限しない場合を含む取引である。
建ぺい率
敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)の割合(%)。
例えば、敷地面積が100平方メートル、その敷地上にある住宅の建築面積が50平方メートルならば、この住宅の建ぺい率は50%ということになる。
建物の建ぺい率の限度は、原則として、用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。
権利登記
土地・建物に関する権利の状況・権利の変動を表示した登記のこと。
権利登記は、一筆の土地または一個の建物ごとに作成される登記記録のうち、権利部に記載される。
現状有姿
「現状有姿」や「現況有姿」と言ったりしますが、「現在あるがままの状態」という意味です。土地や建物を売買する時の契約書に「現状有姿」や「現況有姿」とある場合は、契約時の状態のまま引き渡すということです。
公示価格
法令に基づき国家機関等により定期的に評価されている公的地価のうち、個別の地点、適正な価格が一般に公表されているもので、日本では地価公示法の公示価格を指す。
公図
土地の境界や建物の位置を確定するための地図で、一般に旧土地台帳施行細則第2条の規定に基づく地図のことを指す(旧土地台帳附属地図と呼ばれることもある)
公租公課
租税公課は、租税及び、公的な負担金である「公課」を総称したものである。類似した概念に「公租公課」があるが、こちらは、租税のうち、法人税等を含まない。
不動産取引に関しては、主に固定資産税のこと。
公道
国や地方公共団体(都道府県、市町村、特別区)が指定・建設・管理する道路のことである。一般的に「道路」といわれると公道のことを指すことがある。
公簿売買
公簿売買とは、土地の売買価格をあらかじめ総額でいくらと定め、登記記録の面積と実際の面積が異なることが判明しても「売買価格の増減はしない」とするもので、登記簿売買ともいわれる。また実測はするものの売買代金の清算はしないという場合も公簿売買になる。
固定資産税
固定資産の所有者に課せられる市町村税。
小屋裏収納
屋根と天井との間にできる空間を利用した収納スペースのこと。
さ行
再建築不可
法律上、現在ある建物を壊して新たな建築ができない物件のことを指す。接道義務違反の土地建物、市街化調整区域の土地などが該当する。
差押
国家権力によって特定の有体物または権利について、私人の事実上・法律上の処分を禁止し、確保すること。
更地
手入れがされていない空き地。 建物がなく、すぐにも建物を建てることのできる宅地や工業用地。
市街化区域
都市計画区域の一つ。すでに市街地を形成している区域およびおおむね 10年以内に優先的かつ計画的に市街化をはかるべき区域 。市街化調整区域に対するもの。無秩序な市街化を防止し,計画的な市街化をはかるために,両者を区分したもの 。市街化区域には,用途地域が定められ,公共投資が優先的に行われるなど,その区域内の都市化がはかられる。
市街化調整区域
都市計画法7条によって定められることとなった都市計画区域の一つで,市街化を抑制すべき区域。市街化区域に対するもので,この区域内では原則的に宅地造成などの開発行為が禁じられ ,市街化を抑制することとしている。
敷金
建物の借主が、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保するため、貸主に交付する金銭をいう。
敷金は、契約が終了した場合に、未払賃料等があればこれを控除したうえで借主に対して退去後に返還される。
敷地権
一棟の区分所有建物の敷地に関する権利をいい、登記によって確定する。
分譲マンションなどの区分所有建物を所有するには、建物自体の所有権(区分所有権)と建物の敷地を利用する権利(所有権や借地権であり、敷地利用権といわれる)とを必要とするが、この区分所有権と敷地利用権は原則として分離して処分できないとされており、そのような分離不能な敷地利用権として登記された権利が敷地権である。
私道
私道とは、個人または団体が所有している土地を道路として使用している区域のことである。公道に対する概念であり、誰でも利用できる公道とは性格を異にしている。土地所有者が便宜を図るために、誰でも利用できるように開放している道路もあるが、多くの場合は土地所有者の許可を得なければ通行することは出来ない。
借地権
借地借家法の概念で、建物の所有を目的とする地上権または土地賃借権をいう。なお、借地権の付着した土地の所有権は底地と呼ばれる。
斜線制限
建築物の各部分の高さに関する制限のひとつである。建築物を真横から見たとき、空間を斜線で切り取ったような形態に制限することから、斜線制限と呼ばれる。通風、採光等を確保し、良好な環境を保つことが目的である。
修繕積立金
管理組合が管理費とは別に共用部分や付属施設などの修繕を目的とした長期計画に従って修繕を実施するために、区分所有者から毎月徴収した金銭を積み立てたものである。
管理費と同様、一般的に専有部分の専有部分の面積の割合で月額料金が定められている。
シューズインクローゼット
玄関の横に設置されている収納スペースのこと。 シューズインクロークなどとも呼ばれる。 広さとしては1畳くらいのものが一般的。 シューズインクローゼットは基本的に土足で立ち入ることができ、最近ではより便利に使えるようにするため、玄関側と部屋側の2箇所に扉が設置されていることが多い。
所有権
物を全面的に支配できる物権で,所有者は法令の制限内においてその所有物を自由に使用・収益・処分できる
新耐震基準
建築物の設計において適用される地震に耐えることのできる構造の基準で、1981(昭和56)年6月1日以降の建築確認において適用されている基準をいう。
心理的瑕疵
その場所で過去に起きた出来事にまつわり、通常一般人が嫌悪感を持つ物件をいう。この心理的瑕疵を有する物件が、一般的に、「事故物件」や「いわく付き物件」と呼ばれるものである。具体的には、その物件内において「事故死」や「自殺」「他殺」「孤独死」といった忌まわしさを感じる死に方をした者がいるケースや、「倒産」「暴力団事務所の跡地」などの悪い事象の連鎖が懸念されるケース、「神聖スポット・井戸跡」のように縁起の悪さを感じさせられるケース、「風俗跡」のように生理的嫌悪が否めないケースなどがある。
地震保険
地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による被害を補償する地震災害専用の保険です。
住宅金融支援機構
住宅金融公庫の業務を継承した独立行政法人。2007年4月1日に発足した。所管省庁は、国土交通省住宅局と財務省である。
住宅性能評価書
「住宅性能表示制度」に基づいて発行されるものです。この制度は住宅の性能を、法律に基づいた一律の基準で表示・評価するために作られました。
この制度のおかげで、様々な工法で作られる物件を横並びに比較することが出来るようになり、物件購入の際、専門家ではない私たちでも比較検討がしやすくなったのです。
住宅ローン減税
住宅ローン減税制度は、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。住宅ローン控除と言われる場合もあります。住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、一定の期間、住宅ローンの年末残高の一定割合に相当する金額を、毎年支払う税金(所得税や住民税)から控除してくれるというものです。年間控除額は最高40万円となっていても、あくまでも、自分が支払うはずであった所得税や住民税の中から控除されるもので、必ずしも最高額が控除されるものではないことに気を付けましょう。
重要事項説明
すまい給付金
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。
隅切り
道路の交差点で曲がり角を通りやすくするため、敷地の出隅を切り取ること。 私道においても、位置指定道路や開発道路を築造する場合、新しく築造する道路と既存道路の接する部分の角は、隅切りをすることが規定されている。
スレート葺き
屋根を石質の薄い板で葺くものです。 スレート葺きとは、屋根葺き材に、粘板岩などを加工したスレートと呼ばれる板を用いるものです。 スレートには、天然スレートと人工スレートがあります。
生産緑地
生産緑地法で定められた土地制度の一つ。最低30年間は農地・緑地として土地を維持する制約の代わりに、税制面で大幅な優遇が受けることができる。
セットバック
2項道路(建築基準法第42条第2項の規定により道路であるものとみなされた幅4m未満の道のこと)に接する場合において、建物を建築・再建築する際、道路の中心線から2mとなるよう敷地の一部を後退させることをいう。
なお、セットバックした部分は道路とみなされ、建物を建築することはできない。
接道義務
接道義務とは、建築基準法第43条の規定により、建築物の敷地が、道路に2メートル以上接しなければならないとする義務をいう。都市計画区域と準都市計画区域内でだけ存在し、都市計画決定されていない区域では接道義務は無い。
専属専任媒介契約
媒介契約の一種で、依頼者(売主や貸主)が、他の宅建業者に重複して依頼することができないと同時に、依頼した宅建業者が紹介する相手(顧客)以外の人とは取引できない媒介契約をいいます。 いわば、依頼した業者に全面的に任せるものです
専任媒介契約
媒介契約の一種で、依頼者(売主や貸主)が他の宅建業者に重複して依頼できない媒介契約をいいます。 専任媒介契約を結んだ宅建業者は、指定流通機構への物件登録を媒介契約締結日から7日以内に行い、登録済み証を依頼者に渡さなければなりません。
専有部分
分譲マンションなどの区分所有権建物において、区分所有者が単独で所有している部分のことです。 一般的には住戸部分をいいますが、厳密には、天井・床・壁などコンクリート躯体部分で囲まれた内部空間になります。 これに対して、区分所有権建物において、区分所有者全体で所有している部分は「共用部分」といいます。
専用庭
マンション内で個人的に使用できる庭のことです。 マンションの敷地の一部に、通常は1階部分の入居者用に設けられています。 バルコニーと同じように共用部分ですが、区分所有者に専用使用権が与えられ、使用も管理も任されることになります。 専用庭は、広さに応じて使用料がかかるケースが一般的です。
底地権
底地権とは、借地権者様が地主様から土地を貸り、建物を建てて住んでいる場合において「地主様が土地を貸している権利」の事を指します。
側溝
排水のために道路や鉄道にそって設けたみぞ。
た行
耐震等級
耐震等級とは、建物の強度を表す1つの指標です。品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)に沿った住宅性能表示で、3つの段階に分かれています。
【耐震等級1】
・数百年に一度程度の地震(震度6強から7程度)に対しても倒壊や崩壊しない
・数十年に一度発生する地震(震度5程度)は住宅が損傷しない程度
【耐震等級2】
・等級1で想定される1.25倍の地震が起きても耐えられる
※主に学校や病院などの耐震性能が等級2です。
【耐震等級3】
・等級1で想定される1.5倍の地震が起きても耐えられる
※主に消防署や警察署など防災の拠点となっている建物は等級3です
宅地造成
農地,山林,原野などを宅地に転換して整地し,あるいは沼沢地や水面を埋立てるなどして住宅,工場などの建築敷地や市街地用地を造り出すこと。整地のほか道路の新設,区画割りを行い,上下水道,電気,電話,ガスなどの施設を完備させる。もともと宅地であったところで,土地の形質に改変を加える場合も宅地造成ということがある。
宅地建物取引士
宅地建物取引士とは、宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者であり、宅地建物取引業者が行う、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務を行う、不動産取引法務の専門家である。
宅配ボックス
宅配ボックスは、受取人が留守の時に宅配便や郵便物の受取を代行するロッカー型設備である。宅配ロッカーと呼ばれることもある。留守でも荷物を受け取れるため、平日は帰宅が遅くて宅配物を受け取るのが困難な人や、インターネット通販をよく利用する人にニーズが高まっている。
建売住宅
土地と住宅をセットで販売する新築分譲住宅のこと。 一般的には、まとまった土地をいくつかの区画に分けて、同じ仕様の住宅を何棟か建てて販売する。 住宅が完成してから販売する場合もあれば、設計プランは決まっているが建築中の段階で販売する場合もある。
大規模修繕
分譲マンションの性能を維持し老朽化を防止するために、計画的に行なわれる修繕であって、多額の費用を要する修繕のことである(これに対して多額の費用を要しない計画的な修繕は「小規模修繕」という)。 具体的には、鉄部塗装工事・外壁塗装工事・屋上防水工事・給水管工事・排水管工事などの各種の修繕工事を指している。
団体信用生命保険
住宅ローンを組んだ方が死亡または所定の高度障害状態になられたとき、その保険金で住宅ローンを返済するための生命保険です。 住宅ローンを組む時に、ほとんどの金融機関で団体信用生命保険の加入が義務付けられています。
地役権
一定の目的の範囲内で、他人の土地(承役地)を自分の土地(要役地)のために利用する物権のことをいう。 地役権の設定は、例えば、公道と自分の土地の間にある他人の土地(私道)を通行したり、用水路から自分の土地まで水を引くなどの目的で行う。
地区計画
地区計画とは、都市計画法第十二条の四第一項第一号に定められている、住民の合意に基づいて、それぞれの地区の特性にふさわしいまちづくりを誘導するための計画。 地区計画制度は、ドイツのBプラン制度などを参考に、昭和55年の都市計画法及び建築基準法の改正により創設された。
地勢
高低や山・川の配置など、その土地全体のありさま。
地積
不動産登記法上の一筆の面積をいう。
地積測量図
地積測量図とは、一筆ないし数筆の土地の地積を法的に確定した図面をいう。不動産登記令に基づき、土地の表題登記、分筆の登記等を申請する際には、地積測量図を添付しなければならない。 地積測量図は登記所に保存されており、誰でも閲覧及び写しの交付を請求することができる。
地代
土地賃貸借契約や借地契約において、借主が貸主に支払う賃料のこと。 借地料と同義。 なお地代に消費税は課税されない。
地番
地番とは一筆の土地ごとに登記所が付する番号をいう。主に不動産登記で使用されるほか、住居表示が実施されていない地域では住所をあらわす時にも利用されることが多い。住居表示に関する法律に基づいて市町村が付する住居番号とは異なる。
地目
土地の用途による区分のこと。 土地の登記事項に地目が記されている。登記上の地目と実際の用途は同じとは限らず、異なっている場合もある。課税上の土地の評価は地目によって異なるが、評価上の地目は現況による。
仲介手数料
宅地建物取引業者を通して不動産を売ったり買ったり、あるいは貸したり借りたりする場合に、媒介契約にもとづき、宅地建物取引業者に成功報酬として支払うお金のこと。
媒介手数料(媒介報酬)ともいう。
長期修繕計画
10年から30年程度の期間を対象として、マンションの各箇所に関する鉄部等塗装工事・外壁塗装工事・屋上防水工事・給水管工事・排水管工事などの各種の大規模修繕をどの時期に、どの程度の費用で実施するかを予定するものである。
坪
尺貫法による面積の単位。明治時代の度量衝法で、400/121平方メートルと定義された。これは一辺が6尺(1間)の正方形の面積であり、約3.305 785 124㎡である。いわゆる「1坪=畳2枚」は中京間基準に基づくものである。日本においては計量法により、取引又は証明においては、坪の使用は禁止されており、平方センチメートル、平方メートル、ヘクタール、平方キロメートルなどを用いなければならない。
2×4工法
2×4(ツーバイフォー)工法というのは、アメリカ、カナダ生まれの工法で、1974年に日本で導入された。
木造軸組工法は、柱や梁などの「線」によって建物を組み上げるが、2×4工法は、壁と床、天井などの「面」によって組み上げる。
このことから別名「枠組壁工法」とも呼ばれる。
定期借家契約
平成12年3月1日の改正法施行により、借家契約時に貸主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、賃貸期間が終了すると借家契約も終了し、借家人は退去しなければならないとする契約。
原則として契約の更新はできず、再契約には貸し主・借家人双方の合意が必要である。
抵当権
債務の担保に供した物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利。質権とは違って引渡しを要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる、というのが概ね通有的な性質であるが、法域によっては引渡しを要する場合を含むこともある。
手付金
売買契約が結ばれた際に相手方の債務不履行の有無を問わず解約権を認める目的の為、あるいは相手方に債務不履行があった場合には損害賠償もしくは違約金として買主から売主に対して支払われる金銭です。
手付貸与の禁止
宅地建物取引業に対する業務規制の一つで、契約の誘引に際して、手付金の貸付けなど信用の供与をしてはならないという規制をいう。 これに反すると(契約に至らなくとも)監督処分の対象となる。
テラスハウス
2階建ての連棟式住宅のことをいう。
隣家とは共用の壁で連続しているので、連棟建て、長屋建てともいわれる。
各住戸の敷地は、各住戸の単独所有となっている。
天袋
床の間のわき、または押入れの上部にある、戸棚。
天窓
建物の屋根部分に取り付けられる窓。採光や換気を目的とする。 「ルーフ・ウィンドウ」、「スカイライト・ウィンドウ」「トップライト」とも呼ばれる。
ディスポーザー
家電製品の一種。調理用の流し台の下部に接続している排水設備に直接取り付ける生ゴミ粉砕機。
ディンプルキー
従来の玄関キーのような鍵山がなく、表面に深さや大きさの異なる小さなくぼみ(ディンプル)を付けた形式のキーのことをいう。
ピッキングに強いとされている。2000年代前半にピッキングによる空き巣被害が増加して以来、急速に普及した。
デザイナーズ住宅
建築家やデザイナーが企画・設計に参加して作られた住宅。分譲のデザイナーズマンションや、一戸建てにも波及し、ライフスタイルや価値観の多様化から人気を呼んでいる。素材にもこだわり、建材など大量発注できないので、価値は高くなる傾向にある。
DEN
書斎や趣味の小部屋を指します。 DENは、英語で動物の巣穴やねぐらを意味し、隠れ家、密室、巣窟などの意味でも使われます。 不動産関係では、部屋と呼ぶには狭い、ちょっとこもれる空間といったニュアンスで使われますが、広さや形に明確な定義があるわけではありません。
電気温水器
電気を使ってヒーターをあたため、そのヒーターで水をあたためることでお湯を作る給湯器です。 火を使わないので不完全燃焼やガス漏れなどの心配がありません。
登記識別情報通知書
従来の登記済権利証に代わるもので、不動産の名義変更された場合に新たに名義人となる人に登記所から通知される書類(情報)です。この登記識別情報は、本人確認手段の一つであり、名義人となった後に手続きする際に、登記名義人本人による申請であることを登記官が確認するため、登記所に提供してもらうことになります。
登記簿謄本
土地・建物に関する所在・面積、所有者の住所・氏名、その物件の権利関係等が記載されていて、登記簿謄本とはその写しのことを言います。 不動産登記法により公示が義務付けられているので、手数料(登記印紙で納付)を払えば誰でも交付、閲覧が可能です。
登録免許税
登録免許税法に基づき、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課せられる国税で流通税である。 税率は他の諸税と異なり、千分率で規定されている。
都市計画道路
都市の骨格を形成し、安心で安全な市民生活と機能的な都市 活動を確保する、都市交通における最も基幹的な都市施設として都市計画法に基 づいて都市計画決定された道路です。 都市内の道路は、人や物を移動させるための交通空間であるとともに、人々が 集い、語らい、子どもが遊ぶといった日常の生活空間でもあります。
トップライト
建物の屋根部分に取り付けられる窓。採光や換気を目的とする。
トランクルーム
個人や企業の物品を有料で保管する貸し倉庫。湿度や温度が適切に管理されているものもある。
マンションの室外に設置される収納庫。玄関脇や地下などに設けられることが多い。
取引態様
不動産取引における宅地建物取引業者の立場の違いです。 取引態様とは、不動産の売買や賃貸の取引を行うときに、不動産会社などの宅地建物取引業者がどの立場で関与するかを示すものです。 取引態様の違いによって、宅地建物取引業者の権限と報酬が異なります。 取引態様には、売主・貸主・代理・媒介(仲介)があります。
土壌汚染
土壌中に重金属、有機溶剤、農薬、油などの物質が、自然環境や人の健康・生活へ影響がある程度に含まれている状態をいう。典型七公害の一つ。土壌へ混入した原因は、人為・自然を問わない。
な行
納戸
住宅において普段使用しない衣類や家具・調度品などを収納するための空間。建築基準法で「居室」の基準に適合しないものを言う。
2項道路
建築基準法42条第2項に定められていることから、一般的に「2項道路」と呼ばれており、みなし道路ともいいます。
建築基準法では、原則として幅員が4m以上ないと道路として認められませんが、幅員4m未満でも、建築基準法施行前から使われていた既存道路で、かつ特定行政庁が道路として指定したものは建築基準法上の道路とみなされます。この2項道路に接した敷地に建築物を建築する場合には、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされるため、セットバックすることになります。
二重さっし
既存の窓枠の内側に新たな窓枠を取り付けて窓を二重構造にする事を意味します。 ペアガラスは2枚の窓ガラスと中間の空気層によって構成された複層ガラスを意味します
24時間換気システム
室内の空気の入れ替えを、換気扇などの機械を使って常時行う換気設備のことです。 住宅の場合、2時間で居室の空気がすべて入れ替わる(0.5回/h)だけの換気量が必要と定められています。
二方道路
敷地と前面道路との関係を表したもので、2本以上の道路に同時に接している場合をいいます。 これには、敷地の両側にある(正面と裏面に道路がある)場合と、角地で道路が交差している場合の2つがあります。
任意売却
住宅ローンや借入金等の返済が困難になった場合、債権者は担保権(抵当権等)の実行により債権を回収する事になるが、競売による不動産の売却では現金化までに時間がかかるうえ、市場価格より安くなるケースもある。 そこで、不動産会社の仲介により債権者・債務者の調整を行い、市場で担保不動産を売却すること。
布基礎
木造建物の主要構造部の軸組の下部に連続して設けられる┴字型の断面形状をした鉄筋コンクリート造の基礎で木造住宅などの比較的軽量な建物に一般に用いられる基礎工法。
根抵当権
一定の範囲内の不特定の債権を極度額の範囲内において担保するために不動産上に設定された担保物権のことである。これに対し、通常の抵当権は特定の債権を被担保債権とする。 根抵当権は特定の債権を担保するものではないため付従性がなく、継続的な取引関係にある当事者間に生じる債権を担保することに向いている。
農地
耕作の目的に供される土地のことである。耕地とも。これ以外の土地で、主として耕作もしくは養畜の事業のための採草または家畜の放牧の目的に供されるものは、とくに採草放牧地というが、広義にはこれを含み、農用地ともいう。さらに広い意味での農地は、農畜産物の生産、貯蔵などのための農業用施設用地も含み、農場と呼ばれる。
農地法
耕作者自ら所有することが最も適当であるとの考えにより、耕作者の農地取得の促進、その権利の保護、農地の利用関係の調整などを図ることを目的とする法律。
延床面積
建物の各階の床面積の合計のこと
は行
梁
建造物で柱と柱を連結,上部の重さを支えるための水平な構造材で,多く柱の2倍以上の断面寸法とする。屋根を支える小屋梁,2階の床を支える二階梁などがある。
媒介
宅建業者が宅地建物の売買・交換、借地を成立させるにあたって、契約当事者の両方を紹介すること。
バランス釜
バランス釜は、バランス型風呂釜の通称で、自然給排気式の給排気を採用したガス風呂釜である。 1965年にガスターが他に先駆けて開発したこのバランス釜は公団住宅向け需要を中心に全国的に普及していったが、その後は屋外壁掛け式の給湯器が主流となったために衰退傾向にある。
バリアフリー
障害者や高齢者、子供が生活するするうえでの障壁(barrier)を取り除くという考え方を「バリアフリー」といいます。
具体的には、建物内の段差をできるだけなくしたり、廊下の幅を広げることなどが挙げられます。
これまで、主に交通機関や住戸内で生活する際のバリアフリー化が進められてきました。
バルコニー
建物の外側に張り出し、手すりで囲まれている部分で屋根はない。一般に2階以上に取り付けたものをいい、1階のものはテラスということが多い。
日影規制
日照を確保することを目的した、日影による建築物の高さの制限である。
マンションなどの中高層建築が建築されるようになり、日照阻害の問題が顕在化し日照権訴訟が頻発したことなどから、1976年の建築基準法改正で第56条の2として導入された。
庇
家屋の開口部(窓、出入口)の上に取り付けられる日除けや雨除け用の小型の屋根のこと。
表題登記
まだ登記されていない土地や建物について、初めて登記を作成する登記を「表題登記」といいます。
まだ登記されていない土地や建物とは、海などを埋め立てて新しい土地ができた場合や、新たにマイホームを建築した場合等が該当します。
表面利回り
物件価格に対してどの程度の家賃収入が得られるかという表面的な収益性を表す数値です。 維持管理費など、マンションの保有にかかるコストを計算に入れていませんので、実質的な利回りとは異なります。
ビルトインガレージ
車を格納するスペース(車庫)を建物の一部に組み込んで、シャッターやドアを設置したクローズドタイプのガレージのこと。
吹き抜け
建物の2階または数階にわたって天井がなく上下がつながっている空間。開放感があり、採光が多く得られることから、住宅では玄関ホームやリビングに取り入れられることが多い
複層ガラス
複数枚の板ガラスを重ね、その間に乾燥空気やアルゴンガス等が封入された中間層を設ける形で1ユニットを構成するガラスを指す。中間層は密閉されているため、基本的に中間層の厚さが増すほど断熱性能が高まるが、封入された気体に対流が発生する程厚くなると断熱性能が頭打ちになる。
袋地
民法上は道路に接していない土地をいう。無道路地ともいう。 また、不動産業界においては道路との間に細い路地状の部分を持ち、主たる敷地の大部分が道路と接していないような土地も含む。民法上の袋地を囲んでいる土地を囲繞地といい、袋地の所有者には囲繞地を通行する権利が発生することがある。
付属建物
建物に付属した小屋・勉強部屋・作業部屋・物置・便所などであり、建物登記簿上は表題部に「付属建物」として登記される(未登記の場合も多い)。 付属建物は、通常は建物の従物であると考えられるので、建物が売買されれば附属建物も同時に売買されることになる(ただし、当事者で異なる合意をすることは可能)。
フットライト
廊下や階段の床の前縁に取り付け、足もとから照らす照明。
夜間の安全を図ることを主目的とする。周囲が暗くなると自動的に点灯するものや、人が近付くのを感知してつく人感センサー付き、地震や停電時の保安灯を兼ねているものなど機能も多様。
不動産取得税
土地や家屋を売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)等により取得した人に課税される税金のこと。
不同沈下
建物が不揃いに沈下を起こすことを言います。家全体が均等に沈下するのではなく、一方向に斜めに傾くような状態のことです。
分筆
一筆の土地を数筆の土地に法的に分割することをいう。対義は合筆。具体的には、土地の所有者が登記所に土地分筆登記を申請することにより行う。
変動金利
金利が変動する金利タイプのことをいいます。金利が変動するタイミングは、半年に1回で、4月と10月に見直されるのが一般的です。金利の見直しは、半年に1回おこなわれますが、金利が変動しても、毎月の返済額は借りた時から5年間変わらず、6年目に変わるというルールがあります。また、6年目に毎月の返済額が変わる時、これまで毎月払っていた返済額の、最大1.25倍までを上限として、返済額が変動します。
ベタ基礎
建築物や設備機械の直下全面を板状の鉄筋コンクリートにした基礎をいう。
布基礎と比べ基礎底面の面積が大きいので、荷重を分散させ地盤やスラブに伝えることができ、不同沈下に対する耐久性や耐震性を増すことが可能となるが、コストが掛かる。おもに建築物が重い場合や地耐力が小さい場合に用いられ、必要に応じて杭を設ける。また、床下全面が鉄筋コンクリートになるので防湿対策にもなる。
ペアガラス
複層ガラスと同じ
ペントハウス
建物の屋上に突き出して設けられた階。または屋上に設けた簡単な造りの小屋。エレベーターなどの機械室、屋上への階段室、給水タンク置き場などに利用される。「塔屋(とうや)」ともいう。
保留地
土地区画整理事業で換地として割り当てず(誰にも渡さない土地)を作り、その土地の売却益を事業資金の一部として使う。
このような事業の資金確保のための土地を保留地という。
本下水
本下水とは不動産広告によく記載されている表現で、下水道が整備されており、汚水処理において浄化槽を設置する必要がないことを意味する。
下水道の整備された地域は「下水道の処理区域」という。
ホームインスペクション
ホームインスペクション(住宅診断)とは、住宅に精通したホームインスペクター(住宅診断士)が、第三者的な立場から、また専門家の見地から、住宅の劣化状況、欠陥の有無、改修すべき箇所やその時期、おおよその費用などを見きわめ、アドバイスを行なう専門業務を指す。
住宅の購入前や、ご自宅の売り出し前にホームインスペクションを行なうことで、建物のコンディションを把握し、安心して取引を行うことができるため、近年需要が増えている。
防水パン
室内へ置かれる洗濯機の受け皿。洗濯機の排水用ホースをつなげる排水口がついており、水は、排水用ホースから直接排水口に流される。
ポーチ
洋風建築で、建物本体から庇(ひさし)が張り出した玄関前の平らな場所。マンションでは、共用廊下の途中に門扉を開け、そこから玄関までの空間を実質上はその住戸の専用とすることがあるが、そのスペースをいう。
ま行
埋蔵文化財
地中に埋蔵された状態で発見される文化財である。略して「埋文」と呼ばれることもある。一般には文化遺産保護制度における保護の対象となっている。
間口
敷地や建物を、主要な方向から見た時の幅のこと。
敷地や一戸建ての場合は、道路に接している側の長さをいい、マンションの場合は、バルコニーなど大きな開口部がある側の長さをいう。
ミストサウナ
お湯を霧状にして放出するサウナの事。そのため、熱が身体に伝わりやすく、低温でも通常のサウナと同等の効果がある。また、低温のため身体への負担も軽い。
みなし道路
建築基準法第42条第2項の規定により、建築基準法上の道路とみなされる道のことを、2項道路とも呼びます。
建築基準法の規定では、都市計画区域において敷地が4メートル以上の道路に接していないと原則として建物を建てることはできません。建築基準法第42条第2項の規定は、建築基準法施行前の要件を満たさない敷地を救済するための規定です。
無指定
都市計画区域の外側にある土地のことを「無指定」や「無指定区域」などと呼ぶことがある。
また、「非線引きの都市計画区域」においては、中心部には「用途地域」が指定されているが、中心部以外には「用途地域」が指定されていないことが多い。
そこで、「非線引きの都市計画区域」で「用途地域」がない土地のことを「無指定」と呼ぶこともある。
メゾネット
テラスハウスやマンションにおいて、上下2階にまたがる住戸のことを「メゾネット」といいます。
住戸に吹抜などの広い空間を設けることができるなど、立体的な空間を構成することが可能で、一戸建てに近い空間を生み出すことができます。
面格子
窓の外側に金属製の格子を取り付け、窓から人が入れないようにするもの。防犯のため、キッチン・トイレ・バスルームなどの比較的小さな窓や、マンションの共用廊下に面した窓などに取り付ける。
免震構造
地震や交通振動の揺れを建物に直接伝わらないようにつくられた構造。特殊な積層ゴムなどで建物を支えたり、基礎と上部構造の間を滑りやすい構造などにして地震の揺れを軽減する仕組みとなっている。最近では中高層マンションなどにも採用されるケースが見られる。
木造軸組工法
建築構造の木構造の構法のひとつである。日本で古くから発達してきた伝統工法を簡略化・発展させた構法で、在来工法とも呼ばれている。 木造枠組壁構法がフレーム状に組まれた木材に構造用合板を打ち付けた壁や床で支える構造であるのに対し、木造軸組構法では、主に柱や梁といった軸組で支える。
盛り土
低い地盤や斜面に土砂を盛り上げて高くし、平坦な地表を作る、または周囲より高くする工事。またはそれが施された道路や鉄道の区間。またその工事によって盛られた土砂そのもののことも指す。 河川の堤防、住宅地の開発や道路整備などで平坦な地表が必要なときに行われることが多い。
モルタル
一般的にはセメント・砂・水を練り混ぜたセメントモルタルを指す。表面が硬くて強度が大きく、耐火性があるため、左官材料として広範な用途に用いられている。反面、乾燥による収縮亀裂が入り易い。
や行
床下収納
建物の床下につくる貯蔵場所。室内よりも比較的低温であることから、食品などの貯蔵に多く使用される。
床暖房
床下に熱の発生源を配置することで、部屋全体を温めるシステムを「床暖房」という。
この床暖房のシステムには、大きくわけると、給湯器で沸かした温水を床下のパイプに循環させる温水式と発熱体を内蔵したパネルを床下に設置する電気式の2種類がある。
ユーティリティ
住宅などで、洗濯機・乾燥機・アイロンなどの作業のための設備をまとめて設置した部屋。
容積率
敷地面積に対する建物の延床面積の割合。
例えば100平方メートルの敷地に延べ床面積が200平方メートルの建物を建てると、容積率は200%になる。建築基準法では容積率を住宅地は50〜500%、商業地は200〜1300%と定めているが、都道府県や市町村は都市計画法などに基づき、特例枠をつくることができる。
用途地域
都市計画法の地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としている。住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、第一種低層住居専用地域など13種類がある。 都市計画法に基づいて、おおむね5年に一度、全国一斉に用途地域は見直される。
擁壁
盛り土(もりど)や切土(きりど)個所が土圧で崩壊するのを防ぐための壁状の構造物。無筋コンクリート,石材,煉瓦等で作られる重力式,鉄筋コンクリートで作られる半重力式,逆T式などがある。
浴室乾燥機
浴室に取付けられる設備。入浴時以外デッドスペースとなってしまう浴室に乾燥機を取付ける事で、洗濯物を乾かすシステム。スペースの有効活用と、雨天時に洗濯物を干す事が出来るのが最大の特徴。
ら行
ライフライン
エネルギー施設、水供給施設、交通施設、情報施設などを指して、生活に必須なインフラ設備を表す。
不動産売買においては主に電気・ガス・上下水道等の公共公益設備を指す。
ラウンジ
待合室のひとつで、公共の休憩室やロビー、家庭内の居間や客間など、寛げるスペース。
陸屋根
屋根の形状の一つで、傾斜の無い平面状の屋根のこと。平屋根ともいう。屋上を有効利用出来る事から、マンションや高層ビル等や、コンクリート造の建築物に多く見られる。雨水などの排水のために、ごく緩い勾配の設定と、防水施工が肝要。
リノベーション
建築物の修理、改造。耐震性や省エネ性などの機能を高める、事務所用ビルを居住用マンションに変更するなど、既存の建物を大規模改装し新しい価値を加えることをいう。用途変更や時代の変化に合わせた機能向上を伴う点でリフォームと区別することが多い。
リフォーム
住宅の増改築、内部の改装をいう。間取りの変更や外回りの模様替えの意味としても広く使われるようになった。和室や洋室からフローリングへといったことから、壁や床、天井の断熱性、遮音性を高めたり、台所や浴室の器具を替えるなども一種のリフォームである。近年地価高騰により住み替えがむずかしくなったため、いま住んでいる住宅をリフォームして住み続ける傾向が強まっている。
緑化地域
都市緑地法において平成16年に創設された制度です。 良好な都市環境の形成のために、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある 区域を緑化地域として都市計画に定め、一定規模以上の敷地で建築物の新築や増築を行 う場合に、敷地面積の一定割合以上の緑化を義務付けるもの(緑化率規制)です。
ルーバー
羽板と呼ばれる細長い板を、枠組みに隙間をあけて平行に組んだもの。 羽板の取付角度によって、風・雨・光・埃・視界などを、選択的に遮断したり透過したりすることができるため、柵や塀などとしてや、照明器具やエアコンなど隠すことなどの、建築物をはじめとしてさまざまな箇所で用いられる。
ルーフバルコニー
マンションなどで階下住戸の屋根部分を利用したバルコニーのこと。ルーフテラスと表現する場合もある。
礼金
建物の賃貸借契約を締結する際に、借主から貸主に対して、謝礼として支払われる金銭をいう。
契約が終了しても通常、借主に返還されない。
レンジフード
キッチンのコンロ上部に設置する排気設備。 油汚れなどから羽根や筐体・シャッター等を汚さないようにするためのフィルターが市販されており、フィルターを内蔵した製品や、羽根を油汚れを落としやすい素材にしたものも発売されている。付着した油が滴下するのを防ぐため、下部に油受け皿を装備したものが多い。
煙の拡散を防ぐため、フードを設置してその中に設置するのが一般的であるが、フードと一体になったタイプもあり、レンジフードファンと呼ばれることも多い。
路地状部分
袋地の道路から敷地への延長部分をいいます。 道路に接する間口が狭く、奥まったことろに位置する変形敷地の通路部分をいいます。 建築基準法では、建物の敷地は4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。 道路から奥まった敷地は路地状敷地と呼び、この路地状部分は敷地の一部となります。
路線価
市街地的形態を形成する地域の路線に面する宅地の、1㎡当たりの評価額のこと。課税価格を計算する基準となるものであり、相続税や贈与税の基となる相続税路線価と、固定資産税や都市計画税・不動産取得税・登録免許税の基となる固定資産税路線価がある。単に「路線価」と言った場合、相続税路線価を指すことが多い
ロフト
建物の最上階または屋根裏にある部屋を指す。天井の下でなく直接屋根の下にあり、倉庫などに使われる。こうしたロフトを住居用に改造した、天井の高い空間を備えた集合住宅は「ロフト・アパートメント」と呼ばれる。 日本の賃貸物件などでは、天井を高くして中二階を設けて梯子などで昇降できるようにしたものを指す。
ローン特約
金融機関やローン会社からの融資を前提として不動産を購入する場合に、予定していたローンが不成立になると、不動産の購入ができなくなる可能性があります。 そこで、予定していたローンが不成立になった場合は、売買契約を白紙に戻すことができるといった特約を売買契約書の条項に盛り込むことがあります。 これを「ローン特約」といいます。