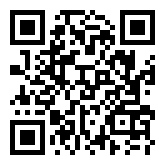不動産購入時の諸費用について
不動産購入時の様々な諸費用について
不動産購入には物件価格以外にもそれぞれのケースに応じて様々な費用が必要になります。
資金計画を立てるときには、あらかじめ全体を把握しておかないと思わぬ失敗を生みかねません。
とはいえ、実際にかかる金額は物件によって大きく異なる場合が多く、具体的な金額を出すのは難しいものです。
ここでは各種費用についてポイントをまとめてあります。
仲介手数料
仲介手数料とは不動産の取引が成立した時にはじめて発生します。
それまでにかかる調査費や交通費などはすべて当社負担となりますので、当社から仲介手数料以外の請求は一切ありません。
仲介手数料の金額は、成約価格によって変わります。詳しくは下記をご参照ください。
売買価格が
200万円以下の金額の場合 売買価格×5%+消費税
200万円~400万円以下の金額の場合 売買価格×4%+2万円+消費税
400万円超の金額の場合 売買価格×3%+6万円+消費税
住宅ローン関係の費用
住宅ローンを組んで不動産を購入する場合の費用です。
現金で購入する場合は必要ありません。
融資事務手数料
住宅ローンの取扱手数料です。金融機関により異なりますが、3~10万円程度の金融機関が多いです。
また、下記の保証料が不要の金融機関の場合、事務手数料が保証料と同じくらいの金額になる場合が多いです。
そのため保証料不要とは言っても全体ではあまり変わらないケースが多いです。
保証料
民間金融機関では住宅ローンの借り入れと保証会社への加入がワンセットになっているケースが多いです。
ローンの返済が滞ってしまった場合などに、保証会社から金融機関へ代わりに支払いを行うためのものです。
保証料については金融機関や申込者、借入年数などで大きく金額が代わってきます。
一例を挙げると民間金融機関で35年ローンを組んだ場合、借入金額の2~3%程度となります。
また、保証料については借入時に一括支払いのタイプと、金利に上乗せするタイプの2パターンを選べる場合が多いです。
団体信用生命保険料
ほとんどの金融機関で住宅ローンとセットになっている生命保険で、一般に「団信」と呼ばれています。
住宅ローンを借りた人が、死亡した場合や高度障害になってしまった場合に保険会社が残ったローンを全額支払ってくれるものです。
健康状態に問題がある場合には加入ができないため、住宅ローンを組む場合には健康状態も大きく関わってきます。
保険料は最初から金利に含まれている場合が多いです。
また、金利に上乗せすることで手厚い保障を受けられる三大疾病タイプなどの商品がある金融機関も多いです。
フラット35適合証明取得費
フラット35とは民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の全期間固定金利の住宅ローンです。
フラット35を利用するには、一定の技術水準や床面積等の条件を満たした住宅であることを証明する適合証明が必要になります。
資格を持った建築士が現地調査を行い適合証明を発行します。
新築住宅の場合は売主の指定する建築士に依頼となる場合が多く、費用は10~15万円程になります。
土地家屋調査士への報酬
新築住宅の場合のみ必要になる費用です。
建物の測量費用と表題登記手続きによる土地家屋調査士への報酬となります。
ほとんどの場合、売主の指定する土地家屋調査士に依頼となり、10万円程度となります。
司法書士への報酬
登記手続きの専門家である司法書士への登記手続き代行費用です。
新築住宅など売主が業者である場合には、売主の指定する司法書士へ依頼となります。
土地の筆数などで大きく異なりますが、5~20万円程度となります。
また、登記手続きにはこれとは別で登録免許税という税金が必要になります。
各種税金について
不動産取引には税金関係が大きく関わってきます。
登録免許税(国税)
登録免許税とは法務局へ登記申請する際にに係る税金です。
不動産取引の場合は主に下記になり、様々な軽減税率があります。
・売買・相続・贈与による所有権移転登記
・新築住宅購入の際の所有権保存登記
・住宅ローン借り入れによる抵当権設定登記
軽減税率や税額についてはこちらをご確認下さい(外部リンク:国税庁ホームページ/登録免許税の税額表)
印紙税(国税)
不動産売買契約書は課税文書であるため、作成するためには収入印紙を貼付する必要があります。
また住宅ローンを借り入れする場合の金銭消費貸借契約書も課税文書となります。
契約書の金額により税額は異なりますので、詳しくは下記をご参照ください。
売買契約書 金銭消費貸借契約書
100万円を超え 500万円以下のもの 1千円 2千円
500万円を超え1千万円以下のもの 5千円 1万円
1千万円を超え5千万円以下のもの 1万円 2万円
5千万円を超え1億円以下のもの 3万円 6万円
1億円を超え5億円以下のもの 6万円 10万円
(2020年3月31日までの軽減税率)
不動産取得税(県税)
不動産を取得する際に係る税金です。
不動産取得時ではなく取引終了後しばらく経ってから納税になるため、忘れていて慌てることがないようにしないといけません。
様々な軽減措置があり、一般的な新築建売住宅や築浅の不動産は実質的に無税となることも多いです。
軽減税率や税額についてはこちらをご確認下さい(外部リンク:埼玉県ホームページ/不動産取得税)
消費税(国税・地方税)
売主が個人でなく宅地建物取引業者など課税業者の場合のみ課税される税金です。
土地に対しては非課税で、売買金額のうち建物部分についてのみ課税されます。
広告での不動産価格は全て税込価格の記載になっているので別途考える必要はありませんが、手数料などの諸費用についても消費税が課税されます。
固定資産税・都市計画税清算金(地方税)
火災保険料・地震保険料
損害保険の一種で、火災だけでなく台風や落雷・水害などの被害によって生じた損害を補償する保険です。
建物と家財に対する保険があり、様々なプランがあります。
地震保険はその名の通り地震に対しての被害を補償する保険で、火災保険に付随する保険となっているので地震保険のみ加入はできません。
住宅ローンを組む場合は火災保険は必須となっている場合が多くなります。
また、新築住宅などでは売主指定の保険会社が必須となっているケースもあります。
リフォーム工事費
中古物件の場合はリフォーム費も考えておく必要があります。
場合によってはかなりの高額になるため、事前に見積もりをとっておきましょう。
オプション工事費
新築物件の場合でも、入居時に必要になるものがオプションになっているケースも多いです。
網戸やカーテンレール、照明などが付いているか確認しましょう。
こちらも場合によってはかなりの高額になるため、事前に見積もりをとっておきましょう。
その他の費用
一般的にかかる大きな費用は上記の通りですが、まだまだ費用がかかるケースは多いです。
物件やお客様の内容や要望によって諸費用は大きく変わってきますのであくまで一例としてお考え下さい。